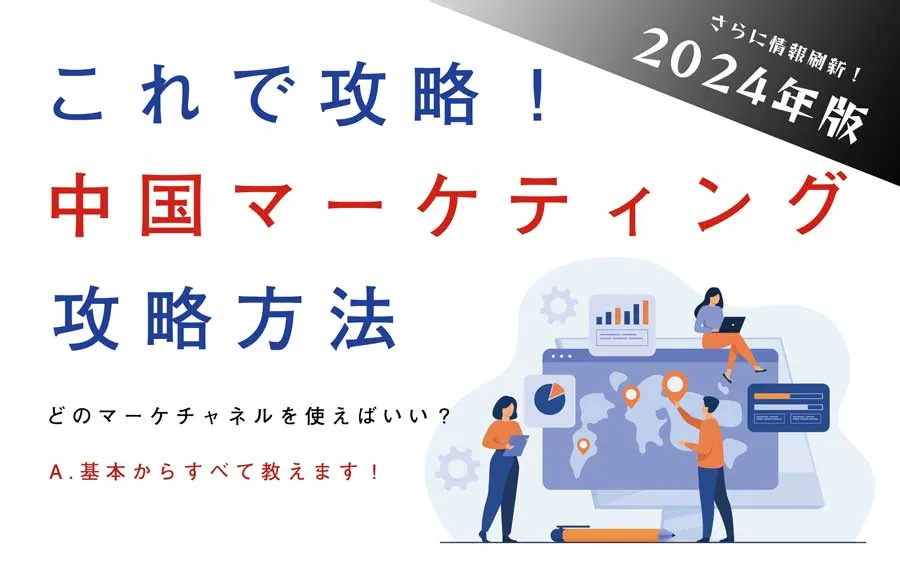新型コロナウイルスの影響による行動制限がほとんどなくなり、コロナ禍前の状態にほぼほぼ戻ってきたインバウンド観光業界。
たくさん押し寄せる訪日観光客に対して、「自社のサービスをアピールしたい」「私たちの商品をぜひ買って欲しい」と、プロモーションを検討されている企業さんも多いのではないのでしょうか。
その中で忘れがちなのが、「コロナ禍前とコロナ禍後では、プロモーション環境が大きく違っている」ということ。
特に中国では、コロナ渦中に大きく成長した「越境EC」の存在を忘れてはいけないですし、コロナ禍前は今ほど小紅書(RED BOOK)や抖音(TikTok)が主流のSNSではなく、現在は若干勢いが落ち気味な微博がまだまだ元気でした。
そんな変化したマクロ環境を踏まえた上で、中国においてはプロモーション計画を立てていかなければいけません。
この記事を執筆している2023年12月時点で、中国と日本の就航便は2019年比で100%にはまだ戻ってはいないですが、2024年には間違いなく大幅に回復し、2019年以上になることも見込まれています。
今のうちにコロナ禍後の中国のプロモーション領域におけるマクロ環境を把握し、計画立案の準備を進めていくことをお勧めします。
このコラムは2万文字以上に渡る長文ですが、読めば明日からの中国マーケティングのお仕事に、必ず役立てて頂けると確信していますので、お時間あるときにどうかお付き合い下さい。皆様の中国マーケティングにおける成功を心よりお祈り申し上げていますし、もし弊社ENJOY JAPANがお手伝いできることがあればお気軽にご相談下さい。
以下、中国マーケティング手法4選としておりますが、具体的な手法だけを読みたい場合は第2章の実践的中国マーケティングの章をご覧ください。それでは始めていきましょう。
※本記事に関する情報やデータは、2023年12月時点でのものです。
この記事の初稿は2021年2月にリリースした記事ですが、2024年1月に改訂版として大幅に加筆・修正を行いました。
資料を無料配布中!
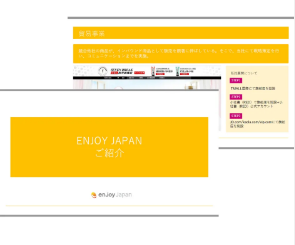
第1章 中国マーケティングの復習と棚卸
とても基本的な内容になりますので、「分かってるよ」「知ってるよ」という箇所は読み飛ばして頂いても結構ですし、復習として読んで頂いても結構です。
中国マーケティングの基本
まず前提として、この記事では、訪日中国人インバウンド、越境ECを含む中国向けアウトバウンドを合わせて、「中国マーケティング」と呼ぶことにします。この第1項では、中国マーケティングを実施する際、事前に明確にしておくべき事を挙げていきます。
読み進めていくと分かりますが、日本でのマーケティングの考え方と大きな違いはありません。中国マーケットだからと言って、変に難しく考える必要
はないのです。
事前リサーチ
何かしらの施策をスタートさせる際、日本マーケットに対しては事前リサーチを実施するのに、なぜか中国マーケットに対しては実施せずにスタートをしてしまう事例が多いという印象を個人的に持っています。
当然のことですが、事前リサーチはターゲットやコミュニケーション戦略、メディアプランなど、意思決定をしていく上で精度を高めるために中国マーケットにおいても必ず実施するべきです。
事前リサーチを実施することで、下記でご紹介する項目を可視化することができ、それをベースに戦略立案をすることが可能になります。
環境分析
市場における自社の強み・弱みを把握します。普段日本で生活をしていると中国現地の情報は中々入ってこないため、特に念入りに調べる必要があります。この際、環境分析のフレームワークである3C分析やSWOT分析などを使います。
セグメンテーション
市場を区切り、各集団のニーズや特徴を把握します。性別、年代、収入、職業は当然ですが、特に中国の場合は住んでいる地域によって住環境や収入などの差が大きいため、ターゲット地域を決めることは日本以上に重要です。
ポジショニング
セグメントして決定したターゲットに対して、自社の商品が提供できる価値を定義します。
(例:乾燥肌の悩みを解決し、自信に満ちた毎日を過ごしてもらう、など)
マーケティング・ミックス
- Product(製品)
- Price(価格)
- Place(流通)
- Promotion(コミュニケーション)
マーケティング・ミックス定義した提供価値を、ターゲットに確実に伝わるように、マーケティング施策を策定します。ここで言う4Pとは上記の4つの項目を指します。
Product(製品)
自社商品の中で、売りたいもの、または売れるものを選定します。日本の製品のまま販売する越境ECにするのか、中国の法律に合わせて販売する一般貿易にするのか、などを判断します。
Price(価格)
中国人消費者は価格に非常にシビアです。ただし、高いものを買わない、という訳ではなく、「良いものをなるべく安く買いたい」という「費用対効果」をとても重視する傾向です。競合や類似商品の価格をベースにして戦略を持って決定します。
Place(流通)
中国人消費者の買い物の中心はオンラインのため、オンラインを中心にスタートするのがおススメです。ただし中国のECプラットフォームはそれぞれに特徴があるため、どのECプラットフォームが最適なのかを見極めます。
Promotion(コミュニケーション)
今まで挙げてきた上記項目が明確になったら、最後にプロモーション戦略の決定です。流行り廃りが早く、独特のルールも多い中国市場の中で最適なプロモーション戦略を立てます。
カスタマージャーニーの考え方
ターゲットがインバウンドの消費者(日本国内)なのか、アウトバウンドの消費者(中国国内)なのかによって、カスタマージャーニーの考え方が異なります。ここではそれぞれをご紹介します。カスタマージャーニーについては奥が深く、単独の記事でも解説しています。詳しくは下記を参照ください。
※関連記事:【2022年版】中国人女性消費者のカスタマージャーニーまとめ
インバウンドの消費者(日本国内)
- 旅マエ
- 旅ナカ
- 旅アト
「旅マエ、旅ナカ、旅アト」という言葉を聞かれたことがありますでしょうか?日本マーケットだけでビジネスをしていると中々耳にする機会がない言葉ですよね。一旦言葉の意味の整理をしましょう。
旅マエ
訪日前のことを指します。旅行を計画・予約するのがだいたい出発日の2~3ヵ月前、ビザを取得するのは1か月前が目安となります。その間に、訪れる場所や必ず買う物などをリストアップします。
ただし、だからと言って必ずしも「買物リスト」にあるものしか買わない、という訳ではなく訪日後に衝動買い的に購入するパターンもあることも忘れてはいけません。近年では情報取得方法が多岐に渡るようになったため、買い物する場所は予め決めておくものの、買うものはその場で決める、という行動パターンが年々強まっている印象です。
プロモーションを実施する場合、このタイミングでいかに消費者に情報に触れてもらい、自社商品に興味を持ってもらうかが重要です。もちろん、さらにその前から「認知度を上げておくこと」が必要なのは、言うまでもありません。特に、観光地などの自治体や施設系の企業は、この旅マエプロモーションが最も力を入れるべきポイントです。
旅ナカ
出発の中国の空港から、到着の中国の空港までの旅行中の期間を指します。ここでは「いかに自社商品のことを思い出してもらうか」と「いかに自社商品や自社施設を好きになってもらうか(=ファンになってもらうか)」が重要です。ファンになってもらえれば、この後の「旅アト」施策で成果を出しやすくなります。
旅アト
帰国後のことを指します。ポイントは「旅ナカで自社商品や自社サービスに触れた消費者に、いかに帰国後にも自社商品を買ってもらうか」です。中国のECサイトで購入するか、または、知り合いの転売を生業としている転売ヤーや日本在住の友人に頼んで代理で買ってもらう「代理購入」のどちらかです。旅ナカで自社商品や施設のファンになってもらうことで、旅アトでの購入率や購入単価が驚くほど上がります。
訪日予定がない消費者(中国国内)
基本的には、日本マーケットでのマーケティングの考え方である「(※1)AISASの法則」と同じと思ってよいでしょう。ただし、最初の「A」である「認知」が、中国マーケットにおいて既に取れているかいないかで考え方が大きく2つに分かれます。
ちなみに自社商品が認知されているのかどうかを調べるには、口コミ投稿アプリ「小紅書(RED)」で口コミ件数を調べるか、中国最大のECサイト「淘宝網(taobao)」に自社商品が出品されているか、出品されていたらどれくらい売れているのか、などを調べると、明確になります。
- A=Attention(気づき)
- I=Interest(興味喚起)
- S=Search(検索)
- A=Action(行動)
- S=Share(共有)
認知が取れている場合…中国SNS上にある程度の口コミが溜まっていると判断できるため(searchの対策と、shareが十分になされている状態)、いかに「自社サービスの情報に触れさせるか=Attention=情報拡散」と「手に取るきっかけを作る=Interest=販売促進」がポイントになります。
より広く情報拡散をさせるためには、当然ですがより「拡散力がある」施策や媒体を選ぶことが望ましく、販売促進は、割引施策やモールのセールキャンペーンに参加をする、ソーシャルバイヤー達に依頼してセールスしてもらう、などの施策が有効でしょう。この「ソーシャルバイヤー」については後ほど説明します。
認知が取れていないのであれば、中国SNS上で口コミを溜めることが優先施策となります(=searchへの対策)。消費者は自分が知らない商品やサービスを購入する際、必ずSNS上で情報検索をします(これは、中国人だけに限らず、日本人もそうですよね)。
検索をした際に、購入に至るだけの十分な情報があるかどうかポイントです。SNS上の口コミが十分に溜まったと判断ができたら、ようやく上記「認知が取れている」でご紹介をした「Attention=情報拡散」と「Interest=販売促進」に移ることができます。
販路をどうするか
この項では、第1項-5でご紹介した『4P』の概念のうち『Place』にあたる「販路」について話をしてきます。中国の消費者に対して自社の商品(ここでは、メーカー・小売りに絞ります)を販売しようと思った場合、大きく4つの方法があります。
- インバウンド・訪日観光客に対して日本で売る
- 越境EC保税区モデルで中国で売る
- 正式な輸出の形式である一般貿易で中国で売る
- 中国独特の「バイヤールート」で売る
これらが大まかな方法です。下記で詳しく説明します。
訪日インバウンド・訪日中国人観光客に対して日本で売る
中国ビジネスをスタートさせていない企業にとって、一番初めにスタートすべきなのが、この訪日インバウンド・訪日中国人観光客に対しての販路獲得です。東京や大阪などのドラッグストアや百貨店を中心に、訪日観光客が多く集まる立地のリアル店舗にいかに集客をして買ってもらうか、というのが基本的な考え方です。
逆にいうと、インバウンドで売れないものが、中国本土だけで売れるはずもないため、ある意味テストマーケティングの機会ととらえてもよいかもしれません。
訪日インバウンド市場の規模や今後の見通し、中国人観光客を集客するためのマーケティングの全体的な設計方法などについては下記の記事で紹介しておりますので、訪日インバウンドマーケティングに力を入れたい方は是非こちらも合わせてご覧ください。
※関連記事:【中国人観光客を集客する】訪日インバウンドマーケティング手法
越境EC保税区モデル売る
下記でご紹介をする一般貿易は時間もお金もかかってしまうため、そういったロスを極力少なくし、シンプル・かつスピーディーに販売までできるように、日本で販売されている商品を、基本的にそのままの仕様で、かつ日本国内から販売できるようにする仕組みが越境ECです。消費者に対して年間の購入金額や販売先の制限があるなど、一般貿易に比べると販路の範囲は狭いですが、はるかにスタートをしやすい販売モデルであることは間違いありません。
越境ECに関しては解説すべきことが多いので、別の記事で詳しく紹介しています。
※関連記事:中国向け越境ECで売上を作る!市場規模から参入方法まで解説
一般貿易で売る
本来であれば自分たちの国で販売している商品を、中国だけに限らず海外へ輸出して販売する場合、その輸出先の国の法律に沿って商品を準備する必要があります。例えば中国で化粧品を販売しようとする場合、現地に法人を設立するか、もしくはパートナーとなってくれる中国企業を探さなければならず、さらに国家薬品監督管理局・通称NMPAに輸⼊化粧品衛⽣許可証明書を申請・取得する必要があります。(NMPAは以前CFDAと呼ばれていたので、旧CFDAと併記されることもあります。)
ここまで聞いてもなかなかハードルが高いですよね。日本では認可されていても中国では禁止されているような成分が入っていたらもちろんその成分を省いた商品にしなければいけないですし、パッケージか裏面のラベルを中国の言語である簡体字で表記をする必要があります。
つまり中国仕様の商品にしないといけないということですね。中国人消費者目線からすると、読めない外国語のパッケージの商品なんて困るので当然と言えば当然です。上記からも分かるように、一般貿易で商品を販売する場合は時間やコストが非常にかかるため、3年から5年をかけて、会社としても本腰を入れて投資をしていく、という覚悟が必要です。
バイヤールートで売る
これは日本人にはあまり馴染みのない販売ルートですが、中国の消費者にとっては一般的です。中国では代理購入を略して「代購」と呼び、日本では「ソーシャルバイヤー」と呼ばれることもあります。
ここでは、総じて「バイヤー」と呼んでいきます。在日のバイヤーと、在中のバイヤーの2つに分かれ、その中でも、アルバイト感覚でやっているバイヤー、仕事として「貿易会社」を設立してやっているバイヤー、などに細分化ができます。
この中で一番狙いたいのは、大きな取引金額が望める貿易会社のバイヤーです。独自の販売ルートを持っていることが多く、場合によってはかなり大きな取引も見込めます。ただ、近年は大規模なバイヤーは減ってきており、バイヤーが取り扱う商品は多種多様になってきております。
以上の4つの販売方法をお伝えしました。そして、上記で「一番初めはインバウンド・訪日観光客に対しての販路獲得」と書きましたが、さらに重要なのが「日本市場で日本人に売れているか?」です。
日本人に売れていないと、リアル店舗の場合はそもそも小売りの販売棚に商品を置くことができないですし、日本で売れていないものをインバウンド・訪日観光客は欲しがりません。
「日本で売れていなくても、中国では売れるのではないか」という勘違いを起こしてしまいがちですが、そんなに甘くはありません。中国の消費者は「日本でも人気商品なのか、売れている商品なのか」というのを必ず調べます。まず日本で売れていて、インバウンド・訪日観光客に売れていないと、一般貿易でも越境EC保税モデルでも、バイヤールートでも、売るのは難しいと思っておいて間違いありません。
第2章 実践的中国マーケティング

ここからはより実践的、かつ明日からでも現場で使えるマーケティング手法をご紹介していきます。ご紹介をする施策以外もかなりたくさんの施策がありますが、私の長年の経験から、不必要と判断した施策は記載をしていません。
インバウンド・訪日中国人観光客編
ここでご紹介する施策は、どれも実績があり、有効と判断できる施策のみです。
インバウンド・訪日中国人観光客に対してのマーケティング/旅マエ編
小紅書(RED BOOK)優先度:高

- 目的:Attention(気づかせる)、Interest(興味喚起)、Search(検索対策)、Share(共有)
- 利用おススメ業種:観光地、小売り、メーカー、商業施設
小紅書(通称RED BOOK)は、2023年10月時点で、月間アクティブユーザー数2.6億人という、中国人女性で知らない人はいないと言われる超有名アプリです。
元々は化粧品の口コミアプリとしてスタートをしたこともあってユーザーの7割を女性が占めており(最近は男性ユーザーも増加中)、その投稿内容は、化粧品やファッションの情報はもちろん、今では旅行や観光情報、ダイエット情報、エクセルの使い方など、幅広く様々な情報が投稿されています。現在では、20代、30代の女性たちにとっての「検索媒体」という位置付けになっているため、検索結果に表示されるように自社のコンテンツを溜めていく必要があります。
この小紅書に自主的に「投稿したい」と思わせるような、映える写真スポットの準備や商品パッケージのデザイン、商品力などが絶対条件です。日本人女性における「Instagram」の使い方と非常に似ています。
施策は中国ではKOLと呼ばれるインフルエンサーや、KOLよりは発信力がないものの、一般人の中では発信力があるKOC(Key Opinion Consumer)中心となりますが、小紅書内に自社アカウントを設けて投稿運用することもできます。
自社アカウントを運用することのメリットは、大きな費用をかけずに小紅書内にコンテンツを貯めていくことができることです。
その他、少額で広告の出稿も可能で、作成した投稿を予算に応じてターゲットにリーチすることができます。また小売業やサービス業の場合、クーポンを掲載することもできますので、販促ツールとして利用することも可能です。
※アプリの詳細は下記の記事をご参照ください
小紅書(RED)とは?中国のリアル美容系情報が集まるアプリ
抖音(Douyin) 優先度:高
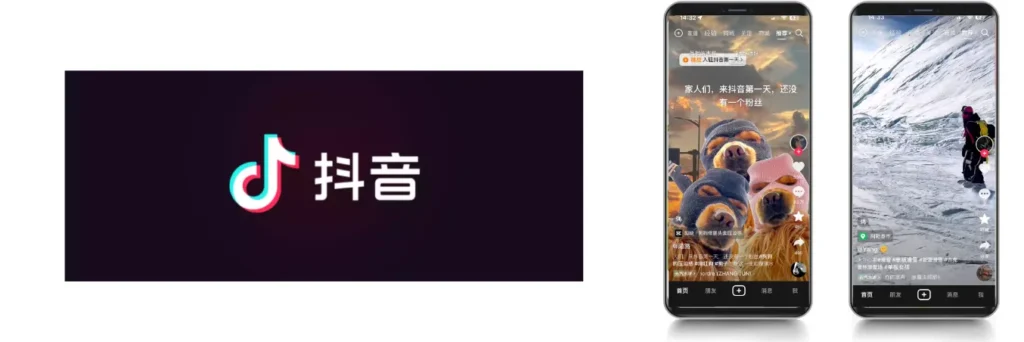
- 目的:Attention(気づかせる)、Interest(興味喚起)、Search(検索対策)、Share(共有)
- 利用おススメ業種:観光地、小売り、メーカー、商業施設
中国版のTikTokである抖音(Douyin)は、2023年10月時点で、月間アクティブユーザー数7.86億人という、今中国で最も勢いがあり、かつ広く利用されているアプリと言えるでしょう。
コロナ禍前から中国で多くのユーザーに利用されていましたが、訪日マーケティング目線ではまだそこまで重要視されておりませんでした。
そのため抖音を上手く活用できている日本企業は「越境EC」に取り組んでいる企業が中心で、訪日インバウンド向けとしてはまだ積極的に抖音でマーケティングを行っている日本企業は多くないと思われます。
とは言え、このアクティブユーザー数を考えると、今後このアプリを無視するわけにはいきません。抖音の活用方法は小紅書と同じくインフルエンサーと公式アカウント運用+広告運用の3つですが、インフルエンサーに関しては発信力のある「KOL」だけで、小紅書のような「KOC」は現在のところあまり意味がないと思ってよいでしょう。また公式アカウントも、「EC機能を設けない日本企業」については現在のところ公式アカウント認証ができないルールになっています。もし企業としての情報を発信する必要があれば、公式ではなく、一般のアカウントとして情報発信をしていく必要があります。
投稿するコンテンツも工夫が必要です。真面目過ぎるコンテンツは再生回数が伸びず、面白いもの、綺麗な映像などインパクトがあるもの、などのほうが再生数は伸びる傾向です。(日本でもTikTokがそういう傾向ですよね。)そのため、企業としてアカウント運用を行う場合も、真面目過ぎず、プラットフォームの傾向に寄ったコンテンツをアップし続ける必要があります。
※アプリの詳細は下記の記事をご参照ください
抖音(Douyin/ドウイン)とは?概要とビジネス活用【中国版TikTok】
携程(Ctrip) 優先度:高

- 目的:Attention(気づかせる)、Interest(興味喚起)
- 利用おススメ業種:小売り、メーカー、商業施設
ユーザー数が3億人を超え、中国オンライントラベル予約の60%をカバーしていると言われる中国最大のOTA(オンライン・トラベル・エージェンシー)。旅行予約の際だけではなく、旅行先を決める段階で情報収集メディアとしても使われています。
広告メニューも多岐に渡っており、小売業向けには成果報酬型クーポン掲載メニューが用意されているので、積極的に利用したいところです。
掲載期間保証のバナー掲載メニューもあるが非常に高いため、一企業が訪日客へのアプローチを目当てに出稿するのはお勧めできません。
そんな中一番のお勧めは、Ctrip内で旅行予約をした人に対して、Ctrip内でターゲティング広告露出ができるメニューです。日本旅行が確定をしている人たちに対してバナー広告を露出することができるため、非常に効率良く情報を当てることができます。
※アプリの詳細は下記の記事をご参照ください
携程(Ctrip/シートリップ)とは? 訪日インバウンド施策に中国OTAを活用
DSP広告 優先度:中

- 目的:Attention(気づかせる)、Interest(興味喚起)
- 利用おススメ業種:観光地、小売り、メーカー
DSP(Demand Side Platform)広告は、日本でもおなじみの広告手法ですが、大枠の考え方は中国も同じです。異なる点は、広告が配信されるメディア(広告枠)と、配信に至るまでのベースとなるアルゴリズムに利用される個人情報です。
配信に利用される情報は、payment決済に使われた決済情報、中国の個人旅行者は必ず取得する必要があるビザの取得情報、旅行サイトでの旅行申込情報、等々です。かなり詳細な情報を使ってセグメントをかけていくため、配信の精度は非常に高いと言えます。
馬蜂窩(マーファンウォー)優先度:中

- 目的:Interest(興味喚起)、Search(検索対策)
- 利用おススメ業種:観光地、小売り
馬蜂窩は中国の個人旅行者にとって欠かすことのできない旅行口コミサービスで、アプリダウンロード数7.6憶以上、ユニークユーザー数、1.3憶以上、毎月の口コミ投稿数は約1,000万件と言われている超巨大メディアです。「次の旅行はどこに行こうかな」というマインドのユーザーが、旅行先を決める時に利用します。
馬蜂窩内で活躍するインフルエンサーの記事が口コミコンテンツのメインとなるため、施策は一定数のインフルエンサーに依頼をして自社サービスを紹介・投稿をしてもらう必要があります。バナー広告などのメニューもありますが、かなり費用が高くなるため、よほど予算がある場合を除きおススメできません。
※アプリの詳細は下記の記事をご参照ください
【中国最大旅行メディア】Mafengwo(馬蜂窩・マーファンウォー)とは?
百度・リスティング広告 優先度:低

- 目的: Search(検索対策)
- 利用おススメ業種:観光地、小売り、メーカー
百度は、言わずと知れた中国No1検索エンジンで、中国国内の約70%のシェアを誇ると言われています。しかしながら、行き過ぎた利益追求主義の影響で検索結果が歪められている、というイメージが広がってしまったこと、検索エンジンとして小紅書が台頭してきたことが重なり、百度を使って検索をする人たちが年々右肩下がりとなってしまっています。特に、旅行などに関する情報検索は小紅書にその地位を奪われてしまっていると言ってよいでしょう。
とはいえ、今でも検索エンジンシェアの約65%を占めていることを考えると、予算をかける意味はあるでしょう。施策は、googleやYahoo!と同様に、リスティング広告運用がメインとなります。
微信(Wechat) 優先度:低

- 目的:Attention(気づかせる)、Interest(興味喚起)
- 利用おススメ業種:観光地、小売り、メーカー
月間ユーザー数が10億人を超える超有名チャットアプリの微信(Wechat)。中国で最も多くの人に利用されているアプリです。
広告としての活用の方法は、微信(Wechat)のフォロワーを多く抱えるインフルエンサーの活用、微信(Wechat)内にある記事アカウントで広告記事を配信する方法、微信(Wechat)内の広告枠にバナー広告を配信する方法、などがあります。
ただし、他のプラットフォームと比較すると、上記のどの広告パターンも、「一人当たりのリーチ単価」は高めです。なので微信(Wechat)を活用する際は、「微信(Wechat)の小程序(ミニプログラム)へ誘導を図りたい」など、明確な理由がある場合に限ったほうがよいでしょう。
インバウンド・訪日観光客に対してのマーケティング/旅ナカ編
旅ナカで一番重要なのは、「自社商品・サービスのファンになってもらうこと」です。中国に帰国をしてからや、再度日本に来た時などに、「もう一度あの商品を買いたい」「またあそこに行きたい!」と思って頂けるような手を打つべきです。
大衆点評 優先度:高
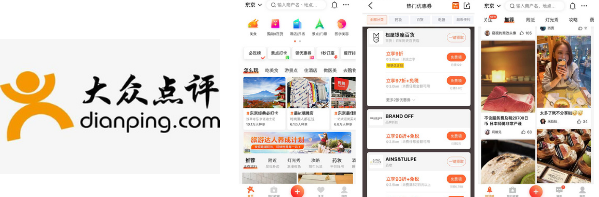
- 目的:Attention(気づかせる)、Interest(興味喚起)、Search(検索対策)、Action(購買)、Share(共有)
- 利用おススメ業種:小売り、メーカー
月間のアクティブユーザー数が2,200万人を超え、訪日中国人のほとんどがスマホにインストールしていると言われています。中国人の方が普段から中国国内で食事や買い物をする際に情報を探したりクーポンを取得したりするアプリで、訪日してからも中国国内で使う時と同じインターフェイスで使用することができるため、非常に使い勝手のよいアプリです。
広告としての活用方法は、アプリ内でのバナーや記事の広告出稿は当然ですが、アプリ内で活躍するインフルエンサーを起用して口コミを投稿してもらう施策、小売りは自店のクーポンを掲載することも可能です。
またアプリ内に企業の公式アカウントを開設できるため、アカウントを設け、定期的に自社の情報発信や広告運用をして意図的に露出を増やすことも可能です。
※アプリの詳細は下記の記事をご参照ください
大衆点評とは?中国最大級の口コミサイト【訪日インバウンド対策も紹介】
小紅書(RED) 優先度:高

- 目的:Attention(気づかせる)、Interest(興味喚起)、Search(検索対策)、Share(共有)】
- 利用おススメ業種:観光地、小売り、メーカー
旅マエでもご紹介した小紅書ですが、旅ナカでも非常に大きな役割を持っています。訪日中国人は日本滞在中も、常に情報を探し、訪れるお店、買う物の情報を探しています。訪れたリアル店舗で気になった商品を、その場で検索して小紅書の口コミをチェックする、というのも一般的に行われています。
観光地の自治体さんは、旅ナカで「目的地」にしてもらうことは難しいですが、観光地で楽しめるレジャーや写真映えするスポットなどは、旅ナカでも訴求して集客につなげることは充分に可能でしょう。また小売業の公式アカウントであれば割引クーポンを掲載することで、「販促」につなげることもできます。割引クーポンを掲載する際は、アカウントの最上位に「固定」をすることを忘れないようにしましょう。
ビーコンターゲティング広告 優先度:低

- 目的:Attention(気づかせる)、Interest(興味喚起)、Action(購買)
- 利用おススメ業種:小売り
ある場所から一定の範囲の半径に入った訪日中国人のスマホに対して、自社の広告を配信するシステムです。セール品やそのお店でしか売っていない商品やキャンペーンなどを準備し、それらの情報を「お店の近隣」にいる訪日中国人に対して訴求するイメージです。
予算の消化期間をコントロールしにくいという課題はあるものの、オフライン店舗への集客に結びつけやすい施策です。
インバウンド・訪日観光客に対してのマーケティング/旅アト編
まず「旅アト」で考えるべき事は大きく分けて2つです。
- 越境ECを活用していかに購入してもらうか
- いかにしてSNSに投稿してもらうか
「越境ECを活用していかに購入してもらうか」について
越境ECは、いかに「旅ナカ」と連動させるかが最も重要なポイントです。近年は以前よりは少なくなってきたとは言え、中国ではまだまだ偽物が多く流通しており、「一度、訪日時に立ち寄ったお店」「日本で買ったあの商品の旗艦店」などの「安心感」があることは中国人の購買行動の背中を押す最も重要な要素の一つです。
この「安心感」を使わない手はありません。訪日時の「旅ナカ」で、いかに自社の店舗や商品の「ファン」になってもらうか、そして「旅アト」である帰国後も、自社の店舗や商品を購入できる環境がある(越境ECサービスを持っている)ことを強くアピールすべきです。
おススメ越境ECサービス:微信小程序(wechat ミニプログラム)

⦁ 「越境ECを活用していかに購入してもらうか」
⦁ 「いかにしてSNSに投稿してもらうか」
インバウンド施策と越境ECで一番連動させやすいのが、微信小程序(wechat ミニプログラム)です。メリットは大きく3つあります。
- 10億以上に利用されているアプリのため、まず間違いなく訪日中国人のスマホにインストールされている
- Wechat paymentが旅ナカでも使われる確率が高く、アカウントフォロワーを獲得しやすい
- 旅ナカで利用できるクーポンを配布し、レジなどで取得を促すことで、アカウントフォロワーを獲得しやすい
さらに、小売業の場合、旅ナカで来店経験がある人と、全くない人で比較をした時に、購入単価も、購入頻度も、来店経験がある人の方が数倍高いというデータが出ています。それだけ、中国の方にとっての「安心感」は重要である、ということが裏付けられるデータだと思います。
ただし、微信小程序(wechat ミニプログラム)で注意すべき点は、あくまで自社アカウントで実施をすること。微信小程序(wechat ミニプログラム)で開設している「日本の商品を扱っているお店」という位置付けの店舗に商品を卸す形では、使う側からすると見え方的に安心感が中途半端のため、意味がありません。極端に言うと「グルになって私を騙そうとしている?」と思われかねません。
さらに、インバウンドと連動させず、単なる「越境ECとして微信小程序(wechat ミニプログラム)を運用させる」というのもおススメ致しません。微信小程序(wechat ミニプログラム)には日本だけではなく、中国を含めて世界中のあらゆる企業が店舗を出しています。そんな環境の中で、知名度もなにもない状態で微信小程序(wechat ミニプログラム)の中で自分のお店を知ってもらう、というのは絶対に無理があるためです。
微信小程序(wechat ミニプログラム)を実施する場合は、必ずインバウンド施策と連動をさせて検討をするべきです。
おススメ越境ECサービス:天猫、京東、拼多多などの大手越境ECプラットフォーム

10億以上に利用されているアプリのため、まず間違いなく訪日中国人のスマホにインストールされています。
- 利用おススメ業種:メーカー
※詳細は動画で解説(YouTubeチャンネル移動します)
【5分でわかる】最新の中国の越境EC事情を知ろう!~2020年度版~
出店費用や運用費用など、プラットフォームによって高い・安いが色々とありますが、集客力がある大手の越境ECプラットフォームを使わない手はないでしょう。ただし、旅ナカで自社商品を手に取ってもらった方に対して、「越境ECのお店があるよ」ということをアピール・訴求をしていく必要があります。
小売業との交渉は必要になりますが、訪日観光客が多く訪れるお店でのPOPや販促物同梱など、旅ナカでの接点をできる限り増やすべきです。
「いかにしてSNSに投稿してもらうか」
方法としては、下記の3つが主だったところでしょう。
余談ですが、ここらへんの仕掛けは中国の化粧品会社がとても上手な印象です。中国の化粧品会社事情についての詳細は、下記のYouTube動画でご紹介をしています。
- SNSを使ったハッシュタグ、リツイート、フォローキャンペーンを実施する。
- 思わず口コミ投稿をしたくなってしまうほどの魅力的なパッケージにする、もしくは商品力にする。
ただし、1と2で気を付けなければいけないのは、「訪日中国人専用の商品、またはパッケージを作ること」は絶対にNGだということです。なぜならば、中国人の目線からすると「中国人向けの商品ということは、自分たちに偽物を売ろうとしているな。もしくは、質が落ちる成分を使おうとしているな」と見えるためです。今まで、「中国人向けに開発した商品が日本で爆発的に売れた」というニュース、目にしたことありますか?ありませんよね?それが何よりの証拠です。爆発的に売れているのは、あくまで「日本人にも売れているもの」です。
まだまだ偽物文化の根強い影響がこういったところに出てきます。あくまで「日本人向け」にパッケージも、商品も開発し、その結果中国の方にも手に取ってもらえる、という流れを作る必要があります。
2を実践するのであれば、微博(weibo)か小紅書(RED BOOK)を使うのがよいでしょう。中国企業は頻繁に実施をしていますが、日本企業の日本法人がインバウンド目的でここまで実施をしている事例はまだ多くはありません。(越境ECでの売上向上を目的としたキャンペーンは日本企業のものでもよく見かけます。)
越境EC保税区モデル編
いわゆる、「越境EC」と呼ばれている施策です。越境ECとは一言で言うと、色々と面倒くさい手続きを極力簡素化して、日本で販売している商品を中国でもそのまま販売できるようにする、というものです。越境ECについての市場規模や利用者像、具体的な進出方法やマーケティング方法などは下記で詳しく紹介しています。
※関連記事:中国向け越境ECで売上を作る!市場規模から参入方法まで解説
そして越境EC成功するには「日本マーケットで売れている」「日本で有名、もしくは中国で有名」「インバウンド・訪日客に売れている」というのが大前提となります。日本でもあまり売れておらず、かつ中国でも知名度がないものは、いきなり売れることは間違いなくありません。(ラッキーパンチはあるかもしれませんが、普通宝くじの1等が当たるようなラッキーパンチを狙ってビジネスはしませんよね?)
以上を踏まえた上で、本コラムでは、お勧めの越境ECプラットフォームと、越境ECの売上を拡大させる施策をご紹介します。
お勧め越境ECプラットフォーム
天猫国際(TMALL.HK)

- 利用おススメ業種:メーカー
言わずと知れた、アリババグループの自社店舗出店型(楽天と同じイメージ)ECプラットフォームで、中国の越境ECプラットフォームでは第2位の規模を誇ります。(1位は考拉海购・通称Kaola)近年、天猫が自社店舗の運営に力を入れている関係で、小売業の企業の新規出店がかなり厳しくなっています。
メリット
- 集客力がある
- 出店をすることで、中国国内でのブランディングができる(=信用度の獲得)
- 二線都市までの都市部のユーザーが多い
- 「本物を売っている」という信頼感がある
デメリット
- 初期費用、運用コストが高額なため、中小企業にとって出店のハードルが高い
- 頻繁にセールが行われるため、運用の手間がかかるし、価格コントロールが難しい
- 三線都市以下の地方ユーザーが比較的少ない
拼多多(ピンドゥオドゥォ)
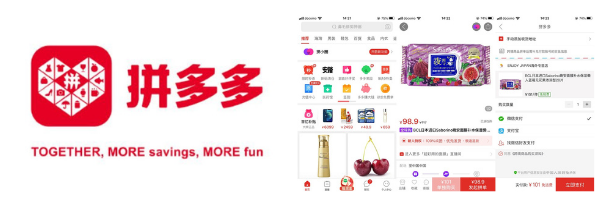
- 利用おススメ業種:メーカー
2020年12月には利用者数がアリババを超えて中国1位(売上額はアリババが1位)となったとも報道された、成長著しい共同購入型ECプラットフォーム(グルーポンのようなイメージ)です。越境ECのサービスは2019年にスタートと、他の越境ECプラットフォームと比較をすると後発なため、まだまだ出店をしている日本を始めとした海外企業は少なく、安売りが前提のプラットフォームであるため、そもそもの参入ハードルが非常に高いと言わざるを得ません。
メリット
- 集客力がある
- 越境ECサービスをスタートしたばかりで日本を始めとする海外企業が少なく、まだ先行者メリットを享受しやすい
- 初期費用、運用費用を比較的安く抑えられる
- 三線都市以下の地方のユーザーが多い
デメリット
- 「安さ」で成長をしてきたプラットフォームのため、価格競争に巻き込まれる可能性が高い
- 越境ECサービスをスタートしたばかりのため、仕組みがまだ未成熟
- 偽物が多い
- 二線都市までの都市部のユーザーが少ない
※関連動画:【5分でわかる】今、中国で最も勢いがあるECプラットフォーム「拼多多」を詳しく解説!
微信小程序(wechat ミニプログラム)
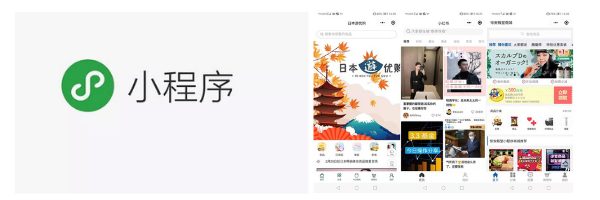
- 利用おススメ業種:小売業、メーカー
中国人に一番使われているチャットアプリ・微信(wechat)内に自社オリジナルのアプリを立ち上げてそのアプリ内で店舗運営をする、というイメージです。色々なサービスがある中で、このwechat ミニプログラムは、自社でのカスタマイズの自由度が高い分、逆に「目的を明確にしてスタートをしないと、最も形骸化しやすいサービス」であるとも言えます。
また、出店はしやすいものの出店後のマーケティングがとても難しく、すでにある程度の認知されているブランドやサービスでなければ成功させるのは難しいと個人的に考えています。
上記でご紹介をしたように、他のお店に「卸す」ことも可能ですがお勧めしませんので、ここではあくまで自社で店舗を設ける場合として、話を進めていきます。
メリット
- ポイントカードや限定クーポンの配布など、自社でコントロールがしやすく、カスタマイズもしやすい
- 顧客情報を管理でき、かつ囲い込みができるため、CRMを回しやすい
- Wechat paymentを導入している小売りは、連動を図りやすい
デメリット
- 広告を実施したり、リアル店舗と連動を図るなどを実施しないと、アカウントを持つだけではフォロワー数も売上も増えない
- 広告を実施する場合、費用対効果が悪くなることが多い
- カスタマイズをすればするほど、開発費用が高くなる
小紅書(RED)

- 利用おススメ業種:小売業、メーカー
上記でもご紹介をしてきましたが、中国のInstagramとも言われる若い女性たちの圧倒的な支持を集めるアプリです。中国の美容関係の情報はすべて小紅書に集まると言っても過言ではありません。
元々が美容関係の口コミアプリとしてスタートをした背景もあり、ECサービスに関しては後発で、会社としてECに注力をしようとしたりした時期もあれば、天猫や拼多多には勝てないと悟ったのか注力をやめる時期もあったりと、紆余曲折している印象ですが、近々は「ライブコマース」に活路を見出して頑張ろうとしている印象です。とは言え、まだまだ天猫や拼多多ほどの販売力はないため、あくまでメインプラットフォームの補完的な位置付けとして考えておくべきでしょう。
メリット
- 元々美容関係の口コミアプリからスタートをしているため、女性ユーザーが多く、ターゲットを絞りやすい
- 美容関係の商品を販売するには、相性が良い
- 自社アカウントで情報発信と一般ユーザーの口コミ管理と合わせて、販売もできる
デメリット
- 販売力が弱い
- 流通網が他の大手モールに比べると、まだまだ脆弱
- 天猫や京東に比べると偽物販売への不信感がある
抖音(Douyin)
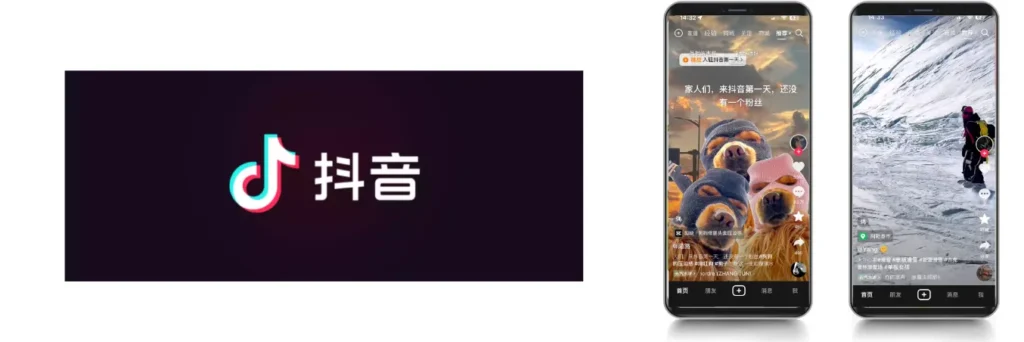
- 利用おススメ業種:小売業、メーカー
2021年、Googleを抜いて最も人気のドメインとなるなど、世界中で大人気となっているTikTokの本家中国版である抖音(Douyin)もECに力を入れています。
EC事業は2020年開始と歴史は短く、越境ECはさらに日が浅いものの、2021年の流通総額(GMV)は8,000億元(約16兆円)を記録するほど好調です。抖音のEC事業については別の記事で詳しく解説をしているのでご参照ください。また、ライバルの快手も同様にEC事業に力を入れており、そちらの記事も合わせてご覧ください。
※関連記事:
抖音(Douyin)のEC「抖音小店」とは?「興味EC」についても解説
快手の越境EC「快手進口店 」と出店・販売方法を解説
越境EC店舗へのおススメ集客方法
越境ECの自社店舗への集客方法は大きく分けて下記2通りです。
- プラットフォームの外から集客を図るパターン
- プラットフォームの中から集客を図るパターン
それぞれご紹介をしていきます。
プラットフォームの外から集客を図るパターン

インフルエンサーの起用
まずは、インフルエンサーを起用することが大前提となります。投稿する形式によってメディアを使い分ける必要があります。
- 写真の投稿:小紅書(RED BOOK)、微博(Weibo)
- 動画の投稿:TikTok(抖音)、快手(Kwai)、bilibili、小紅書(RED BOOK)
- ライブ配信:TikTok(抖音)、快手(Kwai)、小紅書(RED BOOK)
上記各メディアについての詳細は、それぞれ別ブログにてご紹介しています。
外部から集客を図る際に気を付けるポイントは、販売ページへのリンクを無理に入る必要はないということ。そもそも外部リンクをNG、もしくはメディアに対して広告費用を払わないと露出が制限されてしまう、などとしているメディアも多いですが、中国でも「気になったら自分で調べる」のはかなり一般的になっているため、広告色を極力薄くするためにも販売ページへのリンクを無理に入れる必要はありません。
ただし、コメント欄で「どこで売っているの?」と聞かれた場合は、販売しているECサイトのリンクを教えると良いでしょう。
そしてインフルエンサー施策で最近最も気を付けなければいけないポイントは、どんなに有名で大手の「中国の広告代理店」や「日本の店舗運用代行会社」であっても、インフルエンサーの本当の良し悪しを見極められる会社は、限られているということ。
中国のインフルエンサーは「MCN(マルチ・チャネル・ネットワーク)」と呼ばれる組織に属している事が多く、広告案件を依頼する場合、このMCNを管理する会社に依頼をするケースがほとんどです。
このMCNを管理している会社がどんなに有名で大手でも、現場の担当者によっては適当なインフルエンサーをアサインされてしまうケースがとても目立ちますし、進行のやり取りも適当な担当者も多いのが現実です。
具体的には、
- インフルエンサーのアカウントのフォロワーのほとんどが、偽物のアカウントで、数字の水増しをしている。
- 寄せられているコメントが機械的で、「欲しい」「買いたい」など、無機質なコメントばかり。コメント数の水増しをするために、コメントを購入していると考えられる。
- フォロワーの年齢属性が18歳以下がほとんど。⇒フォロワーを購入していると考えられる。
というようなことが実際に起きています。
このようなことが起きているにも関わらず、それに気が付かない日本クライアントがとても多いように感じます。あなたの会社が起用しているインフルエンサーは、本当に大丈夫ですか?この機会に、一度過去のインフルエンサーを見直してみることをお勧めします。
アフィリエイト広告
日本で「アフィリエイト広告」というと、「Webの記事を書いてそこから販売ページへリンクを飛ばす」というのを想像されると思います。中国のアフィリエイト広告の場合、メインは抖音や微信(wechat)を使い、アフィリエイターが抱えるフォロワーたちへの記事配信となります。
すでに中国国内で有名なブランドだと、アフィリエイターたちも意気揚々と望んでくれますが、知名度がいまいちのブランドの場合は、販売価格を安くした上にアフィリエイターの利益を多く設定するなどの交渉が必要です。さらにアフィリエイター一人一人の要望が異なるため、個々での交渉が必要となり、手間がかかる点は注意が必要です。
DSP(Demand Side Platform)広告
※DSP広告の詳細は上記を参照
あくまで、インフルエンサー施策を補完する役割ですが、セグメント制度が高いためDSP広告も有効です。ただし、DSP広告も利用するデータベースによって様々なサービスがありますので、見極めは必要です。
百度リスティング広告
※百度リスティングについての詳細は上記を参照
こちらも、あくまで、インフルエンサー施策を補完する役割ですが、予算に余裕がある場合は実施をしてもよいでしょう。ただし、百度検索自体が、長期目線で見たときに右肩下がりの傾向にあるので、実施をする際はその時の状況を見極める必要があります。
プラットフォームの中から集客を図るパターン
CPM、CPC課金での露出
プラットフォーム内で集客を図る場合は、プラットフォームに広告費用をチャージして運用するCPM、CPC課金での露出が基本となります。プラットフォーム内に商品画像などを露出し、自社店舗ページへの誘導を図ります。露出設定などは、店舗運営パートナーが設定をしてくれるため、出店者は特にノウハウを必要とはしません。普段から広告費用を多く投下すればするほど、優先的に目立つところへ露出を図ることができるようになります。そのため、広告費用を多く投下ができる大手企業が優位となる傾向です。
ライブコマース
KOL、もしくは自社の社員を起用してライブを実施するという基本的なやり方は、プラットフォームの外で実施する場合もプラットフォーム内で実施する場合も、同じです。今、一番売り上げに直結する施策ではないでしょうか。「1日で●●億元を売った!」というニュースを日本でも見かけますが、もちろんこれにはカラクリがあります。このカラクリについての詳細は、当社の公式YouTubeでご紹介していますので合わせてご覧ください。ライブコマースを実施するKOLは、店舗側で決める場合もあれば、運営パートナーから提案される場合もあります。
※関連動画:【5分で簡単解説!】中国最大の買い物祭、W11! その光と影を詳しく解説
一般貿易での中国進出編
大前提として、一般貿易に関しては、手続きにかかる時間と費用を考えると、半年、1年スパンでどうにかなるものではなく、5年、10年としっかりと腰を据えて中国マーケットと向き合う必要があります。成分や商品パッケージなど中国大陸で販売をする上で中国の法律に沿ったものにしなければならず、許可が下りるまでにも年単位で時間がかかると計算しておいたほうが無難です。
また販路の開拓に関しては、自社で一社一社開拓していくこともできますが、中国の商習慣に慣れていない場合や、特別な人脈を持っていない場合は、日本でいうと「卸会社」にあたるような会社と提携し、営業を代行してもらったほうが成功の確率ははるかに上がるでしょう。
一般貿易での販売経路について オンライン編

越境ECでもご紹介をしたECプラットフォームが中心となりますが、「越境」ではなくなる分、プラットフォームの選択肢も広がります。上記でご紹介をしていないプラットフォームだと下記のようなものがあります。
京東商城(JD.com)
言わずと知れた、中国EC業界で売り上げ規模2位のJD.comです。元々PC機器の販売からスタートしたこともあり、「家電製品に強いEC」というイメージが定着しています。JD.comが仕入れをして販売をする「amazon」と同様の直販型がメイン。自社物流網に強みがあり、「早く手元に欲しいときは京東で」というイメージも定着しているのが強みです。
唯品会(VIPSHOP)
海外ブランドメーカーから直接仕入れを行うため、偽物がまだまだ横行する中国において「100%本物の正規品が購入できる」というイメージ戦略で成功をしています。VIPSHOPもJD.comと同様「amazon」と同様の直販型となっています。
蘇寧易購(Suning.com)
蘇寧電器というリアル店舗を持つ家電量販店が立ち上げたECサイト。もちろん家電製品に強みを持っています。2009年に日本のLAOXを買収して傘下に収めています。元々中国国内で家電量販店の中ではリアル店舗数No1だったことで物流網が整備されていて、スピード配送や細やかなアフターケアサービスなどに定評があります。アリババグループ。
一般貿易での販売経路について オフライン編

販売力がある小売りのほとんどは、オンラインの店舗も持っていると思って間違いありません。そのため、「オフライン店舗だけを開拓する」というイメージよりかは「オンラインの店舗と併せて開拓をする」という考えを持ったほうが良いでしょう。
さらに、オフライン店舗を「ショールーム」として、購入はオンライン店舗で、とするOtoO(Offline to Online)の考え方が中国では主流となってきています。特に化粧品のメーカーなどは、オフラインの店舗を写真映えするように装飾し、思わず店に立ち寄って写真を撮りたくなってしまう、というような店作りをしています。オフライン店舗を「ショールーム」、「宣伝媒体」として位置付けているためです。このような手法は今まで日本でもいくつか見受けられましたが、イマイチ定着しませんでしたよね。中国の流れを受けて、今度こそ日本でも文化として根付くでしょうか。注目です。
一般貿易での集客方法事例
基本的に、越境ECでご紹介をした手法がベースとなりますが、「越境」という足枷がなくなる分、できることの選択肢が広がります。具体的には、屋外看板、電車やタクシーなどの交通広告、テレビ広告などなど、その他にもたくさんあります。
また「中国での商売はインターネットが基本」というイメージが強いので、ついついオフラインの宣伝はそこまでやられていないのではないか、と思う方も多いと思いますが、実はオフライン広告を上手く活用している企業も少なくありません。そこで、ここでは特に触れておきたいオフライン広告の活用事例を、2つだけご紹介を致します。
屋外広告看板

W11や6.18など、中国国内でお祭り騒ぎとなるショッピングセール祭りが近づくと、電車広告や屋外広告は、セールの告知で溢れかえります。QRコードを掲載するなどして、オンラインにリンクが飛べるようになっていることが多いですが、目的としてはセールの「認知獲得」「リマインド」がメインです。「オンライン」の売上を上げるために「オフライン」で出稿をしている、ということですね。
オフィスビル・キャラバン

中国の街のオフィスビルを順番に回って、1階スペースで商品ブースを設置し、サンプリングや抽選会などを行う、というものです。中国で大成功を収めている某日本企業が実施しているのを見て、「ここまでやれば、それは成功するよね」と驚き・感心した手法です。オフィスで働く20~40代の男女に確実にリーチしますし、実際に商品を手に取ってもらえるというメリットがあります。これは越境EC用の製品だと中々真似できないやり方ですよね。
バイヤールート編

ソーシャルバイヤー
コロナ禍になる前まで、新宿や心斎橋のドラッグストアなどのお店前で大きなキャリーバックに、買った商品を押し込んでいる中国人を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。また、百貨店などで限定品が販売されるとなると、行列を作っている中国人も多く見かけたと思います。このような人たちが、いわゆる「バイヤー、もしくは転売ヤー」と呼ばれる人たちです。このバイヤーたちも大きく分けて下記の4パターンに分かれます。
- 在日で、かつ個人として活動をしている
- 在日で、かつ会社として活動をしている
- 在中で、かつ個人として活動をしている
- 在中で、かつ会社として活動をしている
以上の4パターンです。一つ一つ説明をしていきましょう。
在日で、かつ個人として活動をしている
一時期多く見かけた中国人のコンビニ店員さんを「ここ2,3年見かけない」と感じたことはないでしょうか?中国人の留学生が少なくなった訳ではありません。コンビニから姿を消したのは、コンビニでアルバイトするよりも、「バイヤー活動をするほうが楽で儲かる」ということに彼らが気づいたからです。
個人で活動をしているのは中国人留学生や主婦、そして会社員の場合は副業として活動をしています。売り上げの規模は月に数万円から中には100万円以上を稼ぐ個人バイヤーもいます。ただし、売り上げが大きくなればなるほど、仕入れから中国への出荷作業など事務作業が多くなるため、売り上げが大きくなった時点で現状維持にするか、会社を立ち上げて集団で活動をするようにするか、選択を迫られるようです。
在日で、かつ会社として活動をしている
ある程度の売り上げを稼げるようになると、「貿易会社」の体裁で会社を立ち上げます。ドラッグストアなどの店舗での仕入れもアルバイトとして雇った「仕入れ」専用のスタッフにやらせたりします。
例えば、抽選でしか販売しない限定品があった場合、抽選の列に並ぶスタッフを大量に雇って並ばせたりもします。月々の売り上げは1千万円~1億円程度でしょうか。ただし、大量に仕入れる分、中国側に大量に買い取ってもらう必要があるため、中国であまり認知度が高くない商品は取り扱わず、知名度が高いナショナルブランドが取り扱いの中心となる傾向があります。
在中で、かつ個人として活動をしている
中国側が入国時の税関チェックが厳しくなったこともあり、コロナ禍になる直前にはかなり少なくなっていましたが、格安航空会社を使って日本と中国を往復し、ハンドキャリーで商品を運んでいた人たちです。今までの流れを考えると、訪日旅行解禁後にこの在中の個人バイヤーが増える、ということはないと思っておいてよいでしょう。
在中で、かつ会社として活動をしている
在日のパターンと同じく「貿易会社」として活動をしています。在日の場合と違い、「日中の往復のコスト」が発生するため、数週間の単位で訪日し、訪日中はドラッグストアやデパートをひたすら回って買い付けをして帰国する、という「買い付けツアー」のような形で活動をしています。
この人たちは新型コロナウイルスの影響で入国禁止となっても、免税対象の資格が切れる半年間は日本に残って活動をしていたと言われています。すごい根性ですよね。
「バイヤー」という言葉を聞くと、私たち日本人はどうしてもネガティブな印象を持ってしまいがちですが、世界に目を向けると「ソーシャルバイヤー」や「せどり」などの言葉は一般的で、転売は世界中で普通に行われています。メルカリやヤフーオークション、世界ではebayが今も成長を続けているのがその証拠です。以上のようなことを考えると、日本企業も中国人の「バイヤー」から目を背けず、どのように上手く付き合っていくかを考えたほうが、未来に向けた一歩になるのではないかと私は考えています。
このバイヤーたちに対してアプローチする方法は、バイヤーと直接知り合いになって一人一人に商品をアピール(営業)する方法が、一番確実で売り上げ規模が大きくなる可能性が高いです。在日のバイヤーであれば、30~50人程度の在日バイヤーを集めた商品説明会や、在日バイヤーの微信グループに情報発信をする、などのアプローチが可能ですが、個人バイヤーへのアプローチとなる場合が多く、継続的な大きな売り上げを見込むのは難しいでしょう。
※ソーシャルバイヤーについては下記の記事でさらに詳しく紹介しています。
中国人ソーシャルバイヤーとは? 代理購入ビジネスに注目すべき理由
第3章 まとめ
概念的なお話から、実践的なお話まで、かなり幅広くご紹介をしてきましたが、いかがでしたでしょうか? 皆さんもよくご存じのように中国は日本以上に変化のスピードが速く、今回ご紹介をしたメディアのサービスやHow toはあくまで2024年1月現在のものであり、1年後の2025年には古い情報になっていたり、全く違うサービスがメインストリームになっていたりする可能性は非常に高いでしょう。その変化のスピードについていくには、常日頃から情報収集を怠らないことが一番重要です。株式会社ENJOY JAPANでは、各SNSメディアを通じて、中国の最新情報を発信しています。ぜひフォローをして頂き、情報収集にお役立てください。それではまた近いうちにお会いしましょう。「再见!」
第4章 おまけ
【おまけ①:中国ビジネスをする上で知らなきゃいけない4つの基本】
- ≪基本1≫独特なネット環境
- ≪基本2≫締め出された世界のインターネットサービス
- ≪基本3≫VPNの存在
- ≪基本4≫中国の「GAFA」と呼ばれる「BAT」が巨大な力を持つ
≪基本1≫ 独特なネット環境
何においても、中国マーケティングを語る上で避けて通れないのは、「グレート・ファイアウォール(中国語名:防火長城、以後「GFW」)」でしょう。GWFは、香港、マカオ(そして台湾も)を除く中国本土のインターネット上に存在する大規模情報検閲システムとその関連行政機関のことです。つまり早い話、ネット上の情報は全て中国政府がチェックしている、ということです。
中国国内から国外のインターネットサービスにアクセスしようとすると、GFWによって国外から中国や中国政府に関するネガティブな情報が入ってこないようチェックされます。皆さんも、中国に出張に行ったときに日本のインターネットサービスにアクセスしようとして、やたら時間がかかった経験はないですか?それは、このGFWが原因の一つですね。
≪基本2≫締め出された世界のインターネットサービス
GWFによって、中国では利用できなくなったインターネットサービスは主要なところだと、
- Youtube
- Yahoo
- LINE etc…
上記の様な世界の主要なSNSは揃って使用することができません。
そのため中国独自のSNSが充実しており、中にはTikTokのように中国発の世界的なSNSも出るようになりました。
※主要SNSのユーザー数などをまとめた詳細は下記よりご覧ください。
【最新資料配布中】中国10大SNS最新ユーザー数まとめ
≪基本3≫ VPNの存在
とはいえ、GFWを乗り越える人々も多くいます。「Virtual Private Network(通称:VPN)」の存在です。VPNに接続すれば、上記の世界の主要SNSにもアクセスが可能になります。
最近、日本のInstagram内で流行しているファッションなどをいち早く取り入れる中国人女子が増えているのは、このVPNのおかけですね。VPNは、法人としてビジネス用に使うことに対しては特に規制はかかっていませんが、個人として「趣味」で使うことは禁止とされています。ただし実際は黙認されている、というのが現状です。
≪基本4≫ 中国の「GAFA」と呼ばれる「BAT」が巨大な力を持つ
世界をリードするIT企業を「GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)」と呼びますが、海外の巨大なインターネットサービスが中国国内でサービス提供ができない環境の中で大きく力を伸ばしてきたのが、BATと呼ばれる3社です。
- B=ByteDance
主要サービス:ショート動画アプリ・抖音(TikTok)、ECモール・抖音小店など - A=Alibaba
主要サービス:ECモール・天猫、決済サービス・alipayなど - T=Tencent
主要サービス:メッセージアプリ・微信、決済サービス・Wechatpayなど
特にAlibabaとTencentは、本来であれば競合となる海外の巨大インターネットサービス会社がいないという守られたマーケット環境の中、中国国内でその存在感を大きく高めていきました。
そして少し前までは「B」は検索エンジンサービスを手掛ける「Baidu」のことを指していましたが、近年の売上が停滞してしまっており、破竹の勢いで成長を続けるByteDanceと入れ替わる形となってしまいました。
【おまけ②:パートナー企業を選ぶ際に気を付けたい事】
自社内で全て対応ができれば問題ありませんが、中々そうはいかないと思います。中国ビジネスを成功させるのに、信頼できるパートナーは欠かせません。そこで、まずは一緒にビジネスをやっていくパートナーはどういった視点で選ぶべきかをお話していきます。
パートナー企業が日本企業の場合
ご存知のように、中国の流行り廃りの速さは日本の比ではなく、かつサービスごとのルールも、事前に何の告知もなく突然変更になったりします。そういった中国の商習慣に合わせるために、常に中国現地とのコミュニケーションを図り、最新情報に触れて、常に知識をアップデートしていく必要があります。
日本企業の場合、このアップデートについていけず、「まだそんな古いサービスを提案しているの?」と思ってしまう企業が、割と多いように感じられます。中国マーケットについて、最新の情報を自分の言葉で話ができる担当者がいる、そして仕組みを持っている企業を選ぶことが望ましいです。
また、「中国の会社と提携をしている」ことを売りにしている企業も多いですが、結局その提携先の中国企業が正しいマーケティング知識を持っているとも限らず、さらに、日本企業側でも中国側の言いなりになってしまっているケースが多いようです。そうなると、中国企業側がどんどん手を抜き、仕事が適当になってくる傾向があります。情報をもらう側である日本企業も、しっかりとした中国マーケティングに関する知識を持っておく必要があるでしょう。
パートナー企業が中国企業の場合
一にも二にも、幅広い意味でのコミュニケーションスキルが重要です。「日本語が話せる中国人」の中でも、言語のレベルにはばらつきがありますし、言語レベルとビジネススキルのレベルがイコールにならないことが多々あります。
さらによく耳にするのが、広告運用などの「オペレーション」はうまいけど、日本の商品をアピールしようとした場合、どうしてもその商品やサービスに対する理解が浅くなる、という面があります。国籍が異なるので当然なのですが、アピールしたい商品やサービスに対して理解が浅くなるとどうしても、消費者との細かいコミュニケーションがすれ違ったり、伝わらなかったりしてしまいます。
特に最初のうちは、担当者が理解をするまで何度も自社の商品・サービスについて話をしていくことをおススメします。また、日本人とのビジネスと一番異なるところは、中国人は得てして自己プレゼン能力が高いため、ついつい言うことを信用してしまう、という点です。過去の経歴や、自分が出来ること、出来ないことなど、日本人の様に「謙虚に少なく見積もる」ということがなく、あくまで「多めに見積もる」のが基本です。
「信用はしても信頼はしない」という言葉にあるように、相手のことは信用をしつつも、小さいことでも大きいことでも、何事も自分の目で確かめて納得をしたうえで見極めることをオススメします。
この記事を書いた人

一貫して営業畑を歩み、前職の広告代理店でインバウンド事業部を立ち上げ目標売上300%を達成し、その実績を買われ2016年にENJOY JAPANに参画。クライアントはドラッグストアとメーカーが多く、徹底してクライアントの売上向上に尽力してきた結果、一度担当したクライアントは必ずと言っていいほどリピートしていく。